はじめに
「高齢の親の通院・介護で、出費がかさむ…」
「介護保険は使ってるけど、医療費もこんなにかかるの?」
年金収入だけで暮らしている高齢者にとって、医療費や介護費の負担は非常に大きな問題です。中には、通院のたびに高額な医療費が発生し、「もう病院に行きたくない」と言い出す方も。
しかし、日本には高齢者の医療・介護費を軽減する制度が複数存在しています。制度を正しく知り、活用することで、経済的な不安を大きく減らすことができます。
この記事では、2025年現在使える「医療・介護費が軽くなる制度」を厳選して5つご紹介します。
医療・介護費の負担が重い!よくある悩み
高齢者やその家族からよく聞く悩みには、以下のようなものがあります。
- 通院のたびに医療費が数千〜数万円かかる
- 介護サービスを使いたくても、費用が心配で申し込めない
- 年金では生活がギリギリで、医療費や介護費の捻出が難しい
- 特別な制度があると聞いたが、どこに相談すればいいか分からない
こうした問題に対応するために、医療・介護費の負担を軽減する公的制度が整備されています。
知らないだけで損をしてしまうケースも多いため、今すぐ確認しましょう。
① 高額療養費制度
高額療養費制度は、医療機関や薬局での自己負担額が、月ごとに上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。
ポイント
- 70歳以上の高齢者は、所得区分に応じて自己負担限度額が決まっている
- 申請すれば後日、払い戻しを受けることができる
- 限度額適用認定証を事前に取得すれば、支払い時点で軽減される
例(70〜74歳・一般所得者の場合):
- 月の医療費:12万円
- 自己負担限度額:約1万8,000円(2025年時点)
- 差額の10万円以上が戻ってくる計算に
💡 保険料の見直しも医療費軽減のカギ!
② 医療費控除(確定申告)
年間の医療費が10万円以上(または所得の5%以上)かかった場合、所得控除を受けることができる制度です。これにより、所得税・住民税が軽減されます。
対象になる医療費の例:
- 通院費・入院費・診療費
- 介護サービス費(医療系)
- 市販薬(一定条件)や交通費(公共機関)
ポイント
- 確定申告が必要(家族分まとめて申告可)
- 医療費の領収書や明細書を保管しておくことが重要
- 控除対象かどうか分からない場合は税務署や専門家に相談
📝 医療費控除の書き方が不安な方は…
③ 介護保険(要介護認定)
介護保険は、要介護認定を受けることで、自己負担1〜3割で介護サービスを受けられる公的保険制度です。訪問介護・デイサービス・施設入所など、多様な支援が受けられます。
利用までの流れ
- 市区町村に要介護認定を申請
- 調査・審査を経て要介護度が決定
- ケアマネージャーとサービス計画を作成
- 介護サービス利用スタート
月額負担の目安(要介護1・1割負担の場合):
- 約5,000〜15,000円で複数サービスを利用可能
✅ 介護費用を抑えるなら、民間保険と併用もおすすめ!
④ 障害者手帳との併用
高齢者でも、身体的・精神的な疾患がある場合、障害者手帳の交付を受けることでさらなる負担軽減が可能です。
主な手帳の種類:
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳(知的障害の方)
特典の一例:
- 医療費の自己負担がさらに軽減
- 各種割引(交通機関・NHK受信料・施設利用)
- 補装具や車椅子の助成金・貸与制度
📌 介護と障害の制度が両立することも!
申請方法や併用ルールについては市役所または福祉事務所へ
⑤ 福祉サービスの無料相談窓口
どの制度を使えるのか分からない…という方は、公的な無料相談窓口を活用しましょう。
代表的な窓口:
- 地域包括支援センター(全国の自治体に設置)
- 福祉事務所(生活保護・障害福祉など)
- 社会福祉協議会(貸付制度・支援金あり)
- 民間の終活支援団体や保険代理店
相談できること
- 利用できる制度一覧の案内
- 申請書類の手続きサポート
- ケアマネージャーや専門職の紹介
📞 制度に強いプロに無料で相談できます!
まとめ:制度を活用して医療・介護費の不安を減らそう
医療や介護にかかるお金の不安は、制度を知って動くことで大きく減らせます。
今回紹介した制度はすべて、2025年時点で高齢者が活用できるものばかりです。
- ✅ 高額療養費制度で医療費の上限を抑える
- ✅ 医療費控除で税金を軽減
- ✅ 介護保険で負担を1〜3割に
- ✅ 障害者手帳で追加の支援を受ける
- ✅ 公的窓口で自分に合った制度を相談する
そして、こうした制度だけで不安が残る方は、終活保険や民間の介護保障保険も検討しましょう。
💡 制度の理解 × 保険の活用で、親の老後がもっと安心に!
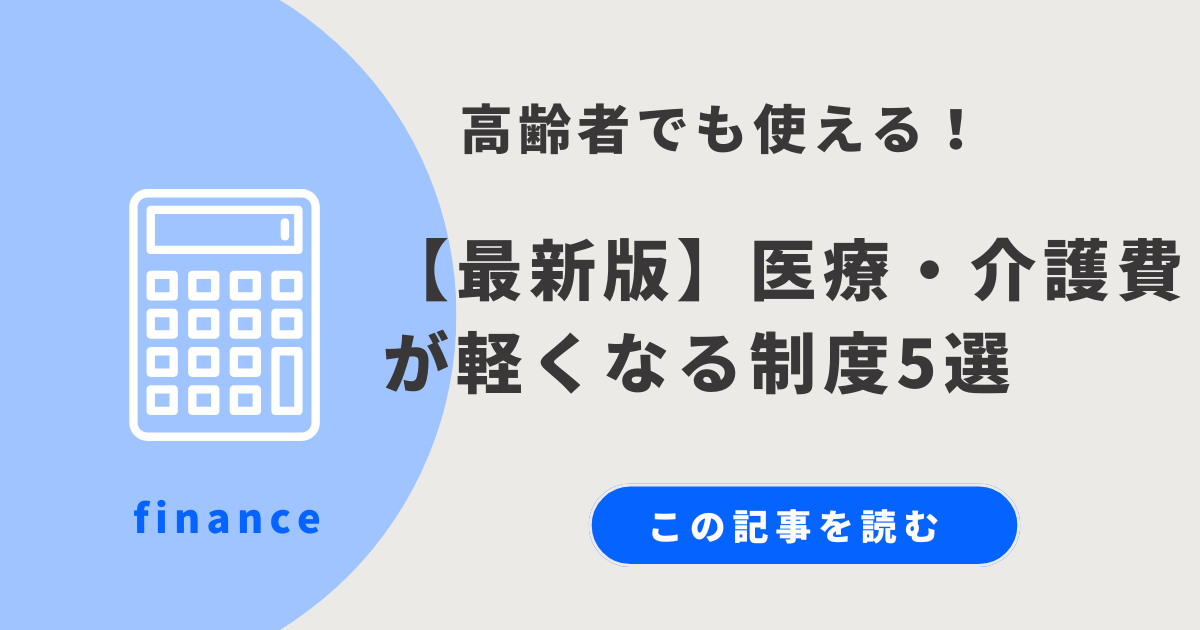
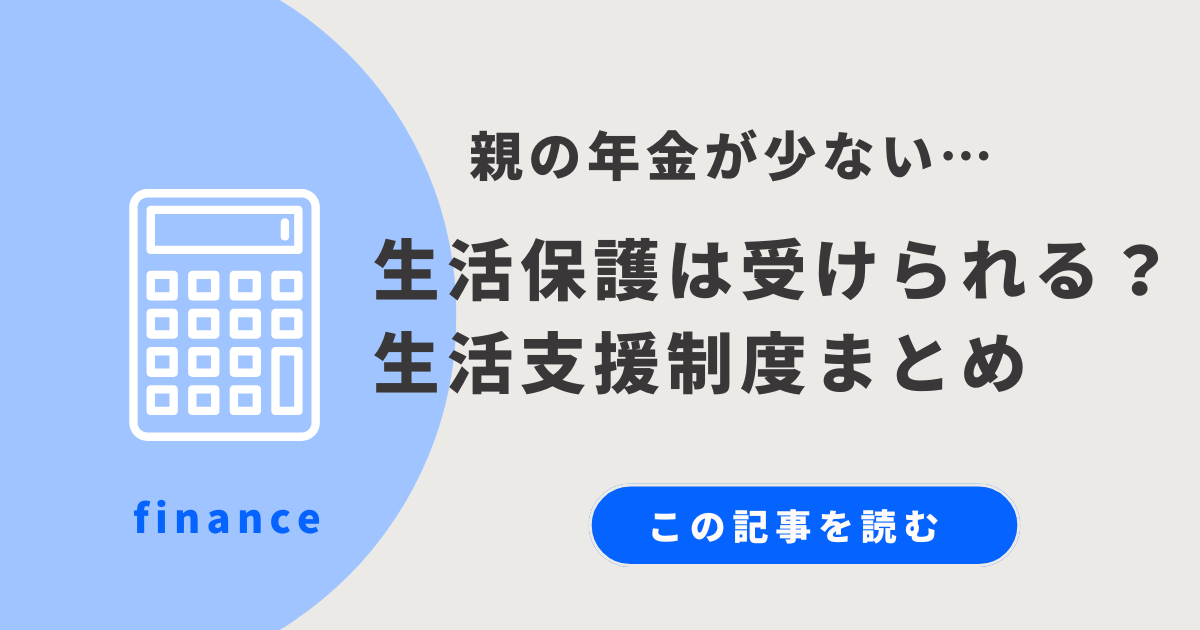
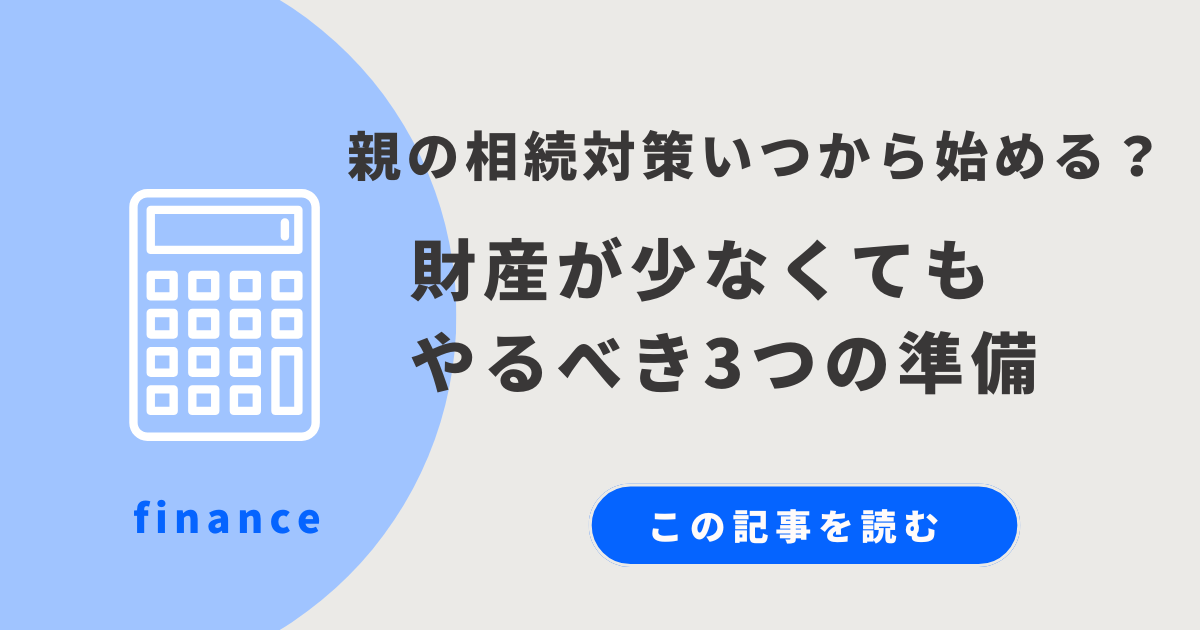
コメント